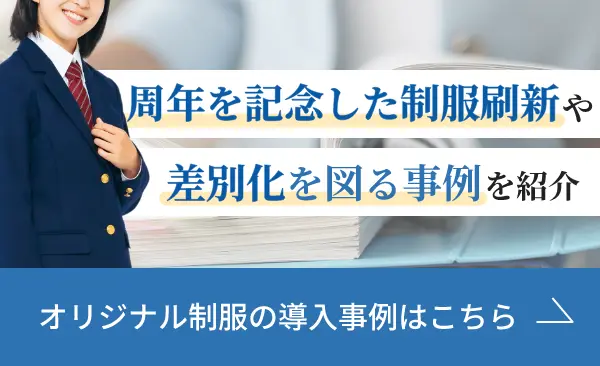「チーム学校」とは?求められている背景や活用できるサービスについても解説
目次
なぜ「チームとしての学校」が求められているのか

教員の多忙化
近年、日本の学校現場では教員の業務負担が増大し続けています。授業準備や指導だけでなく、部活動の顧問、保護者対応、校務分掌など、多岐にわたる業務を一手に担っており、結果として長時間労働が常態化しています。この状況が改善されない限り、教員の心身の負担は増し、教育の質の低下や離職率の上昇にもつながりかねません。
教育課題の複雑化・多様化
少子化や価値観の多様化、ジェンダー問題など、学校が直面する教育課題は年々複雑化しています。さらに、プログラミングや金融教育といった新たな分野が登場し、教育範囲が専門化しています。こうした中では、一人の教員がすべてに対応するのは現実的に難しく、専門性を持った多様な人材との協働が必要不可欠です。
このような背景を受けて、従来の「教員がすべてを担う」学校運営のあり方には限界が見え始めています。今後の学校には、教員が本来担うべき教育活動に集中できるよう、業務を分担し合える体制が不可欠です。そこで注目されているのが、学校をひとつのチームとして捉え、多様な人材が連携・協働する「チームとしての学校」という新しい考え方です。「チームとしての学校」の詳細については、次章以降でご紹介します。
「チームとしての学校」とは何か
「チームとしての学校」の在り方については 、文部科学省より”「チームとしての学校」像”と”「チームとしての学校」を実現するための3つの視点”という提言がなされています。
「チームとしての学校」像
「チームとしての学校」像は、下記のように定義されています。
校長のリーダーシップの下,カリキュラム,日々の教育活動,学校の資源が一体的にマネジメントされ,教職員や学校内の多様な人材が,それぞれの専門性を生かして能力を発揮し,子供たちに必要な資質・能力を確実に身に付けさせることができる学校
文部科学省が示す「チームとしての学校」像では、校長のリーダーシップの下で、カリキュラムや教育活動、学校の人的・物的資源が一体的にマネジメントされ、教職員や学校内の多様な人材がそれぞれの専門性を発揮することが重視されています。
この定義は、単なる業務分担にとどまらず、学校という組織全体を「一つの教育チーム」として再構築することを意味しています。それにより、教育活動に多様な専門人材が関与し、教員は教育指導に専念できます。これにより、教育の質が向上し、教員の負担が軽減することが期待されます。
「チームとしての学校」を実現するための3つの視点
「チームとしての学校」を実現するためには、次の3つの視点に沿って検討を行い、学校のマネジメントモデルの転換を図ることが必要であるとされています。
① 専門性に基づくチーム体制の構築
学校全体の取り組みとして、教員がそれぞれ独自の得意分野を生かしながら学習指導や生徒指導などの活動を「チームとして」担い、子供に必要な資質・能力を育むことができるよう指導体制を充実させます。
あわせて、心理や福祉等の専門スタッフを教育活動に組み込み、教員との連携を強化し、専門スタッフがその能力を発揮できる環境を整備します。
② 学校のマネジメント機能の強化
国・教育委員会が一体となって優れた人材を確保するための取り組みを推進します。校長がリーダーシップを発揮できるような体制の整備や、学校の教育目標の下に学校全体を動かしていく機能の強化等を進めます。
また事務職員の資質・能力の向上や、事務体制の整備等の方策により学校の事務機能を強化することも必要です。
③ 教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備
教育委員会や校長等は「学び続ける教員像」の考え方も踏まえ、学校の組織文化も含めて見直しを検討し、人材育成や業務改善等の取り組みを進めます。
文部科学省が提言する「チームとしての学校」像と、その実現に向けた3つの視点は、従来の学校運営を根本から見直し、教員が本来の授業や児童生徒との関わりに集中できる環境を整えるものです。次章では、そうした環境を整える上で必要とされる具体的な専門スタッフについて解説します。
どのような「専門スタッフ」の配置を検討すべきか

「チームとしての学校」を実現するにあたっては、専門スタッフに係る人材の確保も重要な課題です。文部科学省は『「チームとしての学校」を実現していくための具体的な改善方策』の中で、下記のような専門スタッフの配置について検討を加える必要があることを提言しています。
・心理や福祉の専門性等を有する専門能力スタッフ
- スクールカウンセラー
- スクールソーシャルワーカー・授業等において教員を支援する専門能力スタッフ
- ICT支援員
- 学校司書
- 英語指導を行う外部人材と外国語指導助手(ALT)等
- 補習など、学校における教育活動を充実させるためのサポートスタッフ・部活動に関する専門能力スタッフ
- 部活動指導員・特別支援教育に関する専門性等を有する専門能力スタッフ
- 医療的ケアを行う看護師等
- 特別支援教育支援員
- 言語聴覚士(ST)、作業療法士(OT)、理学療法士(PT)等の外部専門家
- 就職支援コーディネーター・地域連携を担当する教職員
出典:文部科学省「チームとしての学校」を実現していくための具体的な改善方策
専門スタッフの配置は、「チームとしての学校」を機能させるうえで重要な要素ですが、それだけでは十分とはいえません。 専門スタッフの配置には予算・人材確保・業務分担といった課題が伴い、すべての学校で十分な体制を整えるのは現実的に困難です。また、専門性が高く多様な教育ニーズに対応するには、校内リソースだけでは限界があります。
こうした背景から、外部の支援サービスを活用することで、教員の業務を補完しながら、教育の質や多様性を高める取り組みが注目されているのです。次章では、民間サービスや企業との連携による具体的な支援例について紹介していきます。
外部の支援サービスの具体例
文部科学省が提言している専門スタッフに加えて、民間サービスをうまく活用することで、教員が本来の教育活動に専念しやすくなります。
課外授業・探究学習をサポートするサービス
課外授業や探究学習の準備には多くの時間と労力がかかり、教員にとって負担となる場合があります。特に、課外授業の内容やテーマ設定、進行管理、成果の評価までを全て一人で担うとなると、負担はさらに増大してしまいます。
課外授業・探究学習をサポートするサービスは、こうした問題解決の一助となる可能性があります。例えば、外部の専門家を講師として招き、出張授業を依頼すると教師は授業準備の負担を軽減することが可能です。また専門家による知識や視点を取り入れることで、より深い学びを生徒に提供できる利点もあります。
学校が外部の専門性を取り入れる中で、近年注目されているのが「服育(ふくいく)」です。これは、課外授業や探究学習の一環としても取り入れられ、子どもたちにとって身近で実践的な学びを提供する新しいアプローチとして期待されています。
課外授業・探究学習に最適な「服育支援」
「服育」とは、衣服を通じて行う教育活動のことを指し、TPOに応じた服装の理解、マナー、自己表現、さらには環境配慮など、幅広い価値観を学ぶ機会を提供する取り組みです。
制服メーカーやアパレル企業と連携した出張授業やデザインワークショップなどを通じて、子どもたちが社会性や多様性を学び、職業観の形成にもつながることが期待されています。「チームとしての学校」の一環として服育を導入することで、外部人材と連携しながら教育の幅を広げることが可能となります。
<学校側から見た服育支援のメリット>
学校にとって服育支援は、教員が担いきれない専門的な内容を外部の専門家と協働することで補完できる点が大きなメリットです。
例えば、服装の意味や社会的背景に関する授業をアパレル業界の専門家が担当することで、実践的かつ現代的な内容を取り入れることができます。また、進路指導やキャリア教育と連動させることで、教育の質の向上にもつながります。教員の負担軽減と教育内容の多様化を同時に図ることができる点でも、「チームとしての学校」の考え方と親和性が高い取り組みです。
<生徒側から見た服育支援のメリット>
生徒にとっての服育支援の魅力は、日常的に着ている衣服を通して、身近で実践的な学びが得られる点にあります。
TPOを意識した服装の選び方や、ファッションを通じた自己表現を学ぶことで、自己理解や自尊感情の向上にも寄与します。また、衣服の製造・販売の現場を知ることで、将来の進路選択や職業観の形成にも役立つでしょう。多様性を尊重する視点から、ジェンダーや個性の尊重について考えるきっかけにもなり、現代的な教育課題にも対応するプログラムとして注目されています。
こうした課外授業・服育といった取り組みに加えて、学校運営の中で近年ますます重要性が高まっているのが「学校広報」です。学校の魅力や活動を効果的に発信することは、生徒募集や地域との信頼関係構築にもつながりますが、日常業務の中で教員が広報まで担うのは現実的には困難です。こうした背景から、広報活動を支援する外部サービスも活用されています。
広報支援を提供するサービス
学校の広報活動は、特に教師が兼任で行う場合、負担が大きくなりがちですが、外部パートナーを活用することでこうした負担を軽減できる可能性があります。
例えば、学校の特色や魅力をSNSや業界紙などのメディアを通じて積極的に発信するサービスがあります。外部の専門家による支援を受けることで、教員の負担を軽減するだけでなく、広報活動における戦略的なアプローチが可能となり、SNS運用やメディアへの掲載支援を通じて学校のイメージ向上を図ることが可能です。
服育を通した出張授業や学校広報サポートはオンワードコーポレートデザインにご相談ください
オンワードコーポレートデザインは、「制服」の企画・提案を通して、学校の課題解決や魅力発信を支援しています。私たちは制服を単なる衣服としてではなく、教育的価値を持つ「服育」の視点からも捉えています。
この考え方に基づき、出張授業ではSDGsやダイバーシティといった社会的テーマを「制服」という身近な題材から考える機会を提供しています。単に知識を伝えるだけでなく、生徒一人ひとりが自分ごととして社会課題を捉え、深く学ぶきっかけづくりを行っています。
さらに、SNSや業界紙を活用した情報発信のサポートにより、学校の個性や取り組みを社会に向けて効果的に発信する広報支援も行っています。
制服、服育、広報。それぞれを切り離さず、一貫した視点で学校をサポートすることが、私たちの強みです。まずはお気軽にご相談ください。